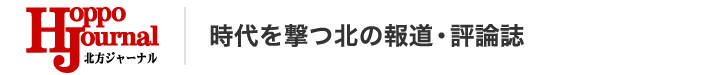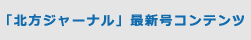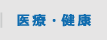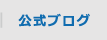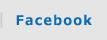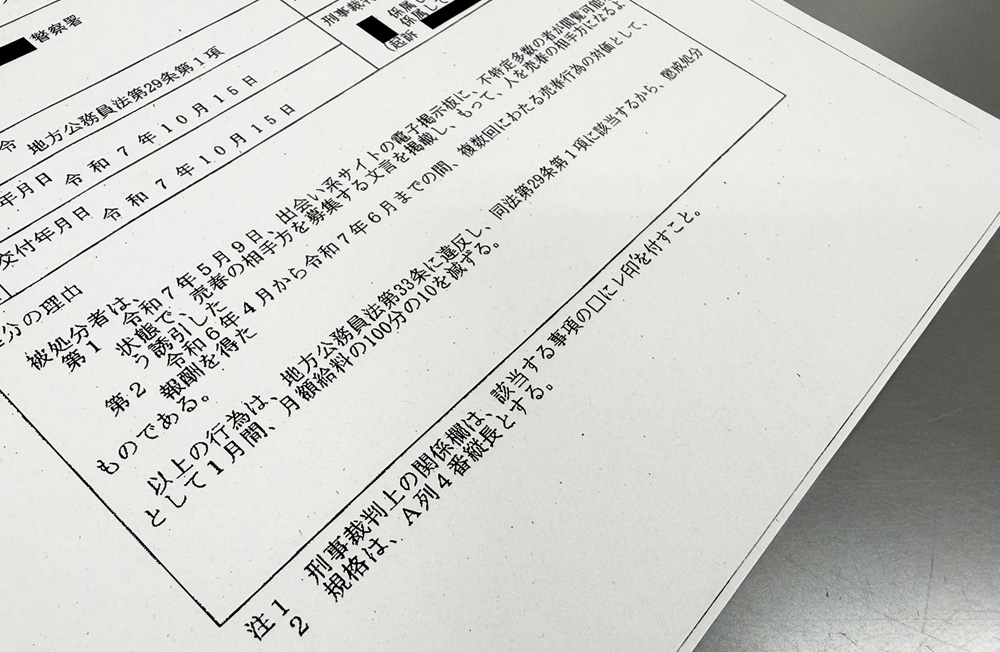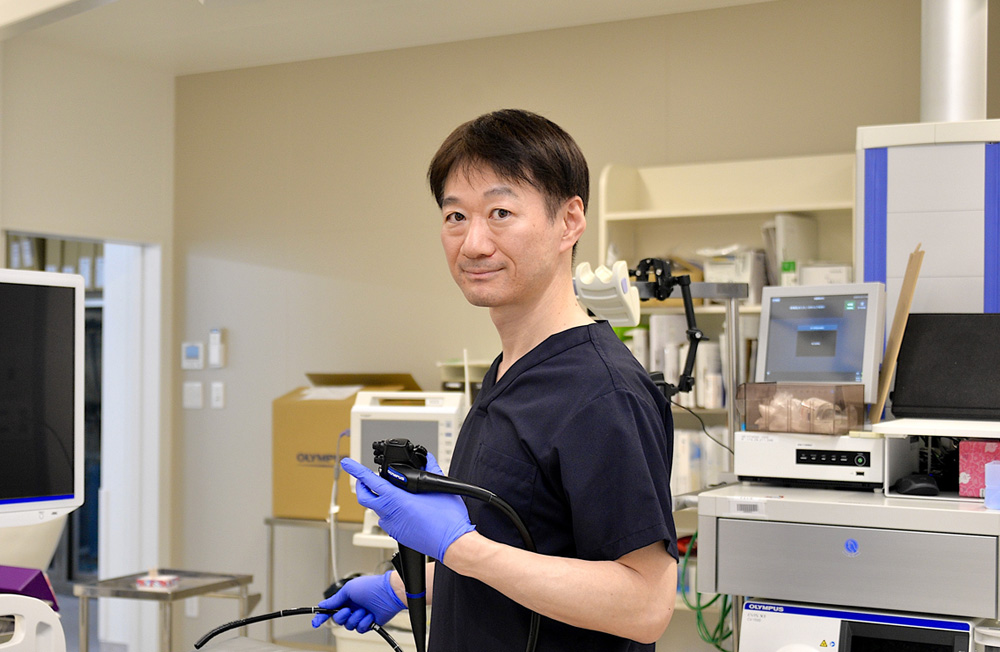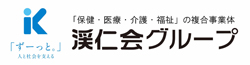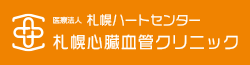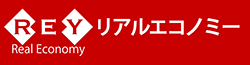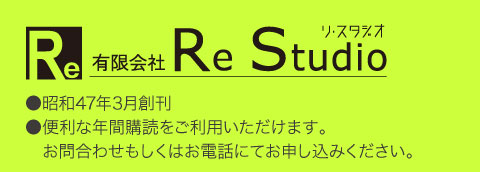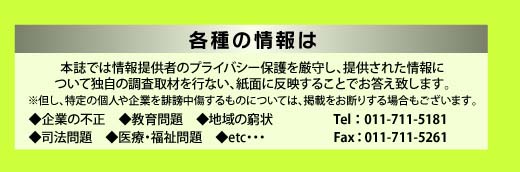堀川裕巳の不動産鑑定士から見た北海道の行方【連載1】
私が不動産鑑定士になるまで
2025年08月号

(ほりかわ・ひろみ)1947 年浦河町出身。74年3月明治大学法学部卒。77年7月社団法人道農都市開発協会入社、79年不動産鑑定士登録。91年北央鑑定サービスを設立し代表就任。米国鑑定士協会(ASA)認定資産評価士(機械・設備)上級資産評価士(不動産)。78歳
運よく開けた専門性の道
人生とは不思議なものだ。筆者が不動産鑑定士という職業についたのは、全くの偶然の賜物である。
田舎の高校を出て、当時流行の新聞奨学生となって大学に入ったものの、当時は学生騒動(全共闘時代)の真っ只中。大学封鎖もあってロクに大学にも行かず、気がついたら卒業。途中から働きながら大学に通ったため就職もままならず、アルバイト先でそのまま働くことになった。
時代は「24時間働けますか」のコマーシャルが流行っていた高度成長期。ひと月に残業百時間は序の口で、2百時間も珍しくはなかった。徹夜も随分したが、このような働き方が3年も続くと、やはり身体が悲鳴を上げダウン。1年間休職して静養したものの、体力がもたずに退社を決意。転職先を探したが、思うように仕事が見つからない。
新聞配達でもやるかと思ったが、その間に知人から聞いた不動産鑑定士の2次試験に受かったら銀行で採用してくれるという話を真に受け、受験を決意した。2次試験(※当時の試験は3段階選抜方式。1次試験は大学の一般教育課程を修めた者は免除)は、民法・経済学・会計学・鑑定理論・行政法規の5科目で、当時は毎日4時間、延べ3日間で行なわれていた。行政法規は○×式だが、他の4科目は論文試験である。
それまで不動産と全く縁のない仕事であったため、とにかくチンプンカンプン。法学部なので民法のことは何とかなるが、経済学・会計学は履修していなかったためバンザイ状態。さらに問題なのは、この試験特有の科目である鑑定理論で、当時の大学で教えているところはなかった。やむなく専門学校に通うことにして、試験は翌年の7月だったので10月から始まるコースに入り、がむしゃらに勉強した。
友人たちには「最初の受験で合格するのは絶対無理」と言われたが、7月の暑い最中、道庁赤れんが庁舎2階の教室で連日の試験をクリアし何とか合格。毎日12時間勉強したせいか、要領や運が良かったのか、よくぞ合格したものだと、今更ながら呆れている。
それはともかく、試験に合格したら銀行に入れるという夢はあっけなく潰れた。世は第二次オイルショックの最中で景気は悪く、合格者に対する求人は皆無。やむなく開発局のOBの鑑定事務所で2年間、丁稚奉公。2年間の実務修習が終わらないと第3次試験(※2006年の制度改正で廃止。現在は2段階選抜方式)を受けられないので仕方ない。
2年間の実務修習を終え第三次試験の受験資格が得られても生活ができないので、農協系の土地区画整理コンサル会社に転職した。最終試験に合格できなければ正社員にしないと言われ、ここで働きながら第3次試験に挑戦し、合格。不動産鑑定士としての仕事のかたわら、土地区画整理コンサルの仕事もやり、農協の人脈もかなり広がった。
目次へ
© 2018 Re Studio All rights reserved.